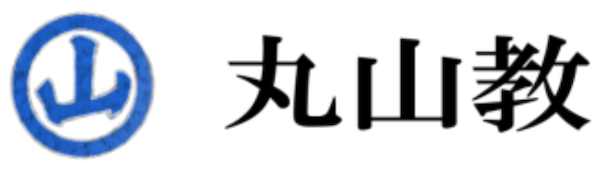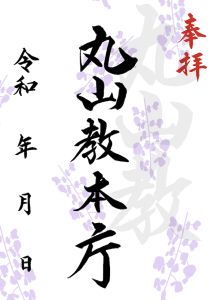神の光 2025年2月号巻頭言 報恩感謝の心をもって
穏やかな新玉の年を迎え、無事元旦祭を泰仕し、連日参詣の信者さんと和やかに接しているうちに、気がつくと松飾りも取れて早大寒を迎えている。教祖百三十天祭の祝祭行まで二ヶ月余り、記念事業の御法殿御屋根の改修工事も無事故にて二月の半ばには完工の目途が立ち、祭事・催事日程等の時間割調整、境内の設営等の準備も余念無きように先例に倣って煮詰めて参りたい。
教祖さまの御信心の最初の転機は、明治元年十二月に教祖さまの奥方サノさまが大病されたことに由来する。この時の教祖さまのご心情は、「家内は家つきの娘、自分は他より養子の身、家内にもしものことがあっては、さだめし両親がなげくであろう。なにとぞ自分の一命をちぢめても、家内の病気を本復させて下さいませ」と、寒中をいとわず夜半に起き出しては水垢離をとって一心に病気平癒を祈願し、これが百日間も続いてようやく本復に至ったという。
これより前、教祖さまは幕末から明治維新にかけて、治安が乱れ、途炭の苦しみに喘ぎ困窮する人民を見るにつけては憂えて、「日本神国、八百万の神という。どこかにこの窮状をお救い下さる神がありそうなものを」との神(親)尋ねの修行と相まって「天下泰平普く人助け」の御本願を立てられる。そのご精神はまぎれもなく、神教にある「身を現世の犠牲に立て」ではないが、自己(自利)を捨て、人の幸せを祈る他利の信心の道である。
この思いは生きとし生けるものすべてに及び、馬を曳いての江戸通いの逸話もしかり、お身祓いを頼まれれば、「馬であっても無駄骨はさせられぬ」と、いちいち馬の荷をおろしては身祓いを施されたと伝わっている。教祖さまの命にたいする慈悲の御心は荒廃した暗い世相の中で一厘の光明を解き放ち、これを慕い、頼りにした人たちが信仰心を磨き、生る力を掻き立てて「和合たんせい」の道を歩んだに違いなく、その先人たちの思いを偲ぶとき、今日一日一日の大切さ、重みも変わって来る。
いよいよ教祖百三十天祭。どうか大いなるもののご加護のお蔭で今日無事あることに思いをいたして頂き、教祖さま、ご先祖さまに報恩感謝の心を手向けよう。