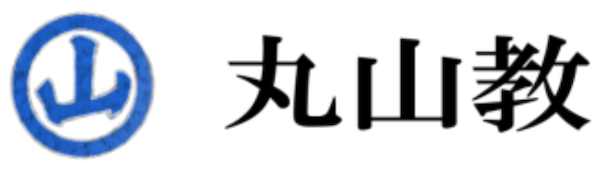神の光 2025年4・5月号巻頭言 天祭を終えて
教祖さまは文政十二年七月十五日卯の刻(午前六時)にご誕生、それより十月ほど前のこと、文政十一年九月の十三夜の日、御生家(清宮家)の門口で経を読む六部を家人が見て、家に呼びいれ茶などを施していたところ、六部は何を感じとったのか、もっていた杖で大黒柱をこつんと突き、「こちらのおかみさんは、近い内に身もちになって男のお子が生まれます。このお子は後きっと出世して名を残すような人になられるから、たいせつに育てなさいよ」と予言したとの生誕説が残っている。
教祖さまの幼名は米吉といい、六歳の時に一月ほど高熱に侵されて生死の淵をさまよう大病を患うが、夢うつつの中に白髪の老人が現れ「これからは信心をせよ」と背中を叩かれて目が覚め、九死に一生を得た宗教体験をお持ちになっている。教祖さまは二十四歳で伊藤家へ婿入り、富士講信心に一層心をよせ、五行身抜きの「光くう心の心の一字に心をとめて座禅修行八年」と申されたように、信心とは心を治めることと悟り、農事に励む中でもひたすら信心修行に励んで、村人から「柳に風(雪)折れなし」の諺にかけて、柔和だが芯が一本通っていることから「柳の六蔵」と呼ばれるような人格者に成長されていく。
この頃は炭薪を積み馬を引いての江戸通い、大菩薩峠の著者中里介山は、教祖さまを評して、「丸山教の御開山様というのは、武州橘樹郡登戸の農・清宮米吉のことであります。この平民宗教の開祖は、馬をひっぱって歩きながら、途中で御祓いをたのまれると、いちいち荷物を積み卸しの二重の手間をいとわず、馬をいたわって、しかして後に御祓いにかかったものであります。この人は、また言う、「おれは朝暗いうちから江戸へ馬をひいて通ったが、ただの一ぺんでも馬に乗ったことはないよ」いやしくも、一教を開くものにはこの誠心がなければならない」と書いている。
幕末から明治維新の動乱の時代、困窮する民を見て「天下秦平・普く人助け」の本願を立て、命を賭した難行苦行の末に「和合たんせい」の御教えを遣された教祖さまの思いと、信奉して人の歩むべき道を生きた先祖にたいし、天祭を無事終えたこの機会に今一度篤と噛みしめ、次代につないでいかなければ申し訳がたたぬ。
感謝の言葉
新緑の風薫る爽やかな季節となりました。皆様方におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、先般斎行致しました教祖百三十天祭の盛儀は、荒天の影響で向ヶ丘遊園駅前までの渡御行列の行幸はやむなく中止となりましたが、両日ともにお陰をもちまして事故もなく、厳粛な中にも和気あいあいのうちに恙なくご奉仕することが出来ました。これも偏に教会長重立の方々を始め奉仕員、教信徒、ご協力下さった地元有志の皆様方の並々ならぬ御たんせいの賜物と深く感謝し、心より厚く御礼申し上げます。
なお、天祭当日は混雑に取り紛れ、あるいは降雨等への対処に追われて、不行き届きの点が多々あった事と存じますが、何卒事情ご賢察頂き、御寛容下さい。
今後は、この大祭を一つの節目として、教信徒の皆様におかれましては、改めて教祖様の「天下泰平・普く人助け」の本額にたちかえり、和合たんせいにつとめて、「日の出に松の御代」の絶対平和・理想世界を実現すべく、一層の御たんせいをお願い申しあげる次第です。
令和七年五月吉日
丸山教本庁